こんにちは!
かめとんぼです。
今回は、DIYで木材の種類を選ぶときに考えたい7つのポイントについて紹介します。
木材の種類選びの7つのポイント
安い木材の種類
避けたほうがいい木材の種類
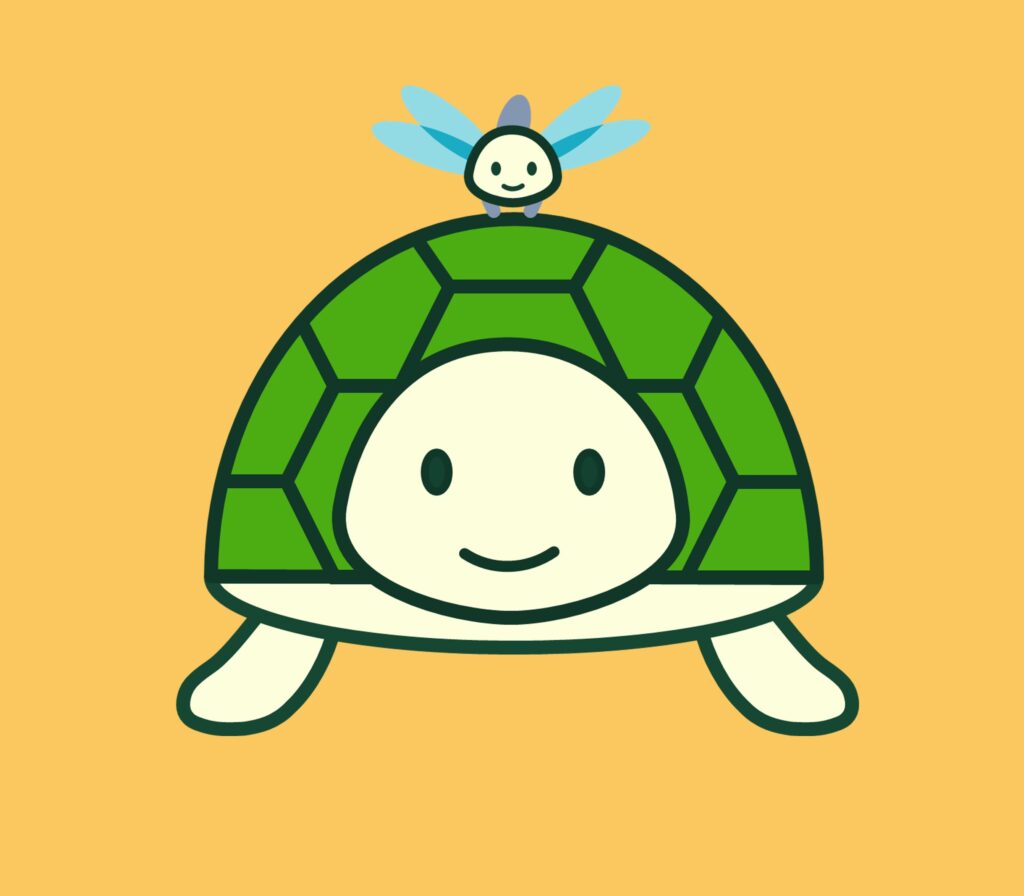
DIYについての知識やポイント、知って得する情報などを紹介します。
現在は賃貸マンションに住んでいて、9割以上の家具を自作しながら理想の部屋づくりを楽しんでいます。
本業は機械設計の仕事をしています。
はじめに
DIYで楽しい作業の1つに、ホームセンターやネット通販での木材選びがあります。
木材の色目、雰囲気を見ながら完成形のイメージを膨らますのは、心も踊ってワクワクしますね。
この木材選びをするにあたっては、見た目や価格などのぱっと目につく項目だけで選びたくなってしまいますが、そこはちょっと待って下さい。
木材には加工のしやすさや強度、耐久性などの気をつけたいポイントが他にもいくつかあり、それらを忘れてはいけません。
これらの項目にも注目して木材選びをすることで、より自分にあったピッタリの木材を選ぶことができます。
そこで今回は、DIYの木材を選ぶときに考えたい7つのポイントについて見ていきます。

木材選びの7つのポイント
木材を選ぶときには、次の7つのポイントをチェックしましょう。
色合い・木目・質感
価格
加工のしやすさ
強度
反りやすさ
サイズ・形
耐久性
順に見ていきます。
色合い・木目・質感
まずはじめに気になるのは、色合い・木目・質感といった木材の見た目・雰囲気です。
木材は、ヒノキやスギといった種類によって見た目が大きく異なるのはもちろん、同じ種類でも個体差があります。
そのため、机や棚などの見た目が気になるものを作るときには、ホームセンターなどで直接木材を見てから購入するのがいいでしょう。
また、木材の色の傾向として寒いところに生える木は白っぽく、暑いところに生える木は赤っぽくなる傾向があります。
白っぽい木材の代表はSPFやホワイトウッド、パイン集成材などがありますが、これらの木材を使うと北米家具のようなシンプルなイメージの部屋づくりができます。
赤っぽい木材の材料としてはスギ、ラワン合板などがありますが、これらを使うと温かみのある部屋づくりができます。
価格
DIYをする上では、価格も大切なポイントです。
大枠のイメージとして、ホームセンターでよく売られている針葉樹は安く、木材屋やネット通販で売られている広葉樹は高い傾向です。
ホームセンターの中で売られている木材の中で安いものは、柱や支柱に使う角材では2×4材(SPF材)やスギ材、机の天板や棚板として使うならラワン合板が有名です。
これらの木材の中には、反りやすかったり表面が荒れているものもありますが、一時的な収納棚や、作業台などの質より低価格さを求める場所にはぴったりの木材です。
加工のしやすさ
既成家具ではなくDIYならではの見ておきたいポイントとして、加工のしやすさも大切です。
DIYではのこぎりを使った木材のカットや、ドリルドライバーを使った穴あけ・ビス打ちをすることが多く、あまり硬い木材や、大きすぎる木材を使うと作業が大変です。
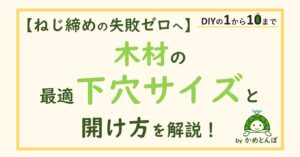
加工しやすい木材としては、2×4材(SPF材)やスギ材は柔らかく、のこぎりでもかんたんにカットが可能です。
また、パイン集成材やスギ集成材といった集成材は、3〜5cmの木材をつなぎ合わせて板材・角材にした木材ですが、成形される時に固い節が取り除かれることが多く、初心者でも簡単に加工をすることができます。

強度
DIYの木材選びでは、強度が弱すぎる木材は避けたほうがいいです。
強度の弱い木材の例としては、キリがあります。
キリはスノコなどに使われる種類で、木の密度が低く、割れたり折れたりしやすいです。
特に、百均で売られている木材はキリが使われていることが多く、重いものを載せる場所での使用や背の高い家具を作るのには避けたほうがいいでしょう。
反りやすさ
幅広の板材や、細長い角材を使う場合には、木の反りやすさ、曲がりやすさにも注意が必要です。
木材の製剤方法の種類には、木をそのまま切り出した無垢材、3〜5cmの木材をつなぎ合わせた集成材、厚さ数ミリの薄い板材を重ね合わせた合板がありますが、この中で特に反り、曲がりが起きやすいのは無垢材です。
無垢材の見分け方として、集成材は板のつなぎ目があり、合板は厚さに重ね合わせた層を見ることができます。
それらのない、無垢の木材が名前の通り無垢材となります。
DIYに使われる無垢材には、2×4材(SPF材)やスギ材などがあり、机の天板などの反りが起きてほしくない場所には集成材や合板を使えないかを検討したほうがいいです。
一方、棚などの多くの面が他の木材と繋ぎ合わされるものでは、あまり反りは出にくくなります。

サイズ・形
木材選びでは、サイズや形も重要です。
簡単なところでは、丸棒や三角棒などの自分では加工が難しい形の木材は、既製品の加工された木材を選ぶことが大切です。
他にも、木材の形に関して知っておきたい種類の1つに2×4材があります。
2×4材は木材のサイズの規格の1つで、断面が2インチ(約5cm)×4インチ(約10cm)の大きさに整えられていることに由来します。
ただし実際には、水分が抜けて縮んだり表面にカンナ掛けをされることで、断面は38mm×89mmのサイズに整えられています。
2×4材であればどこのホームセンターで買っても同じサイズの木材を手に入れることができるため、その使い勝手の良さからDIYでよく使われます。
また、2×4材は他にも1×4材、2×2材、2×6材、2×8材というように断面サイズにバリエーションがあることが特徴です。
2×4材に対して、1×4は厚みが半分、2×2は幅が半分というように規則正しいサイズになっているため、組み合わせる際にも使いやすいバリエーションとなっています。

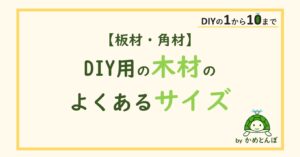
耐久性
ベンチや鉢置きなどの屋外で使うものを作りたい場合には、木材の耐久性にも注意が必要です。
耐久性で気にしたいのは、水のある場所で腐りやすいかどうかです。
DIYでよく使われる2×4材(SPF材)は、水に当たると腐ってしまう木材の代表例で、水に当たらないところで使うか、防腐塗料をしっかり塗って使うことが大切です。
反対に、水があっても腐りにくい木材にはヒノキがあり、檜風呂としても有名です。
このように、木材によって水への耐性は大きく異なるため、自分が使いたい場所、環境に合わせて、耐久性の観点からも見ることが大切です。
まとめ
今回は、DIYで木材の種類を選ぶときに考えたい7つのポイントについて紹介しました。
このブログでは、他にもDIYについての知識やポイント、知って得する情報などについて紹介していきます。
一緒に学んで、楽しいDIYにしましょう。
かめとんぼ
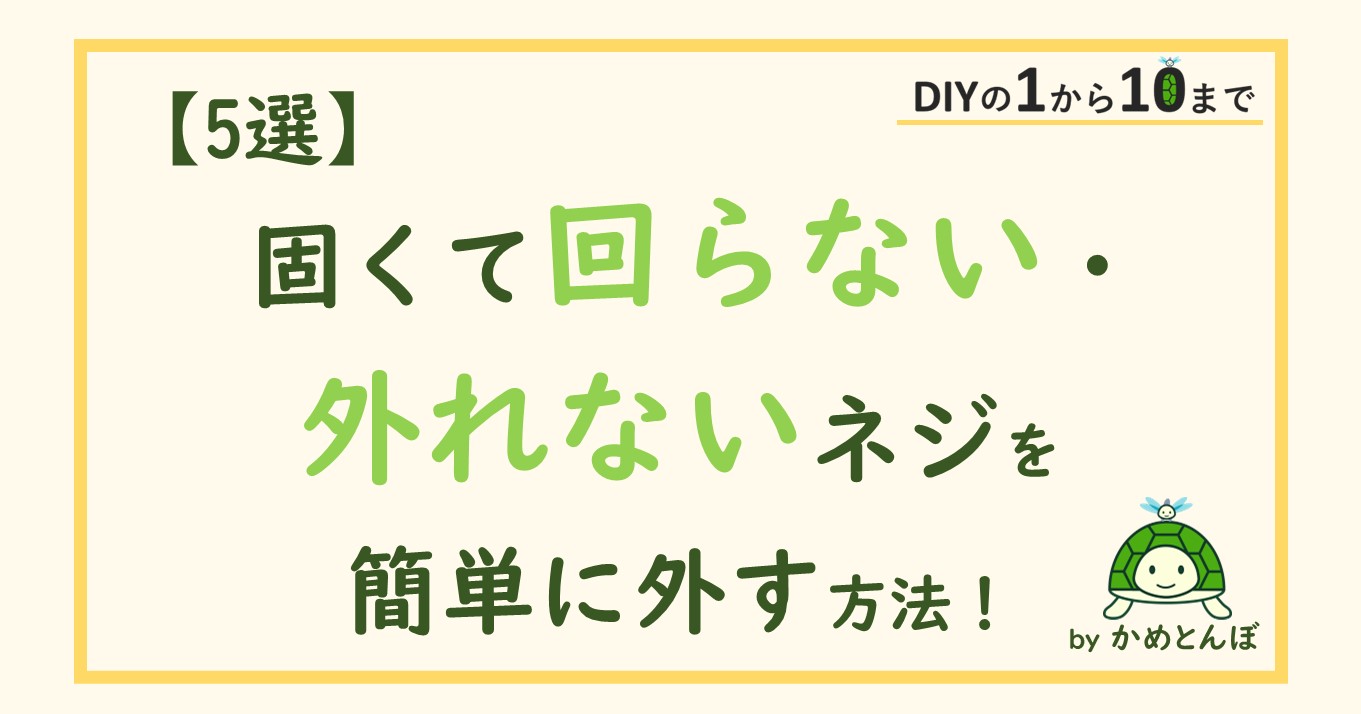
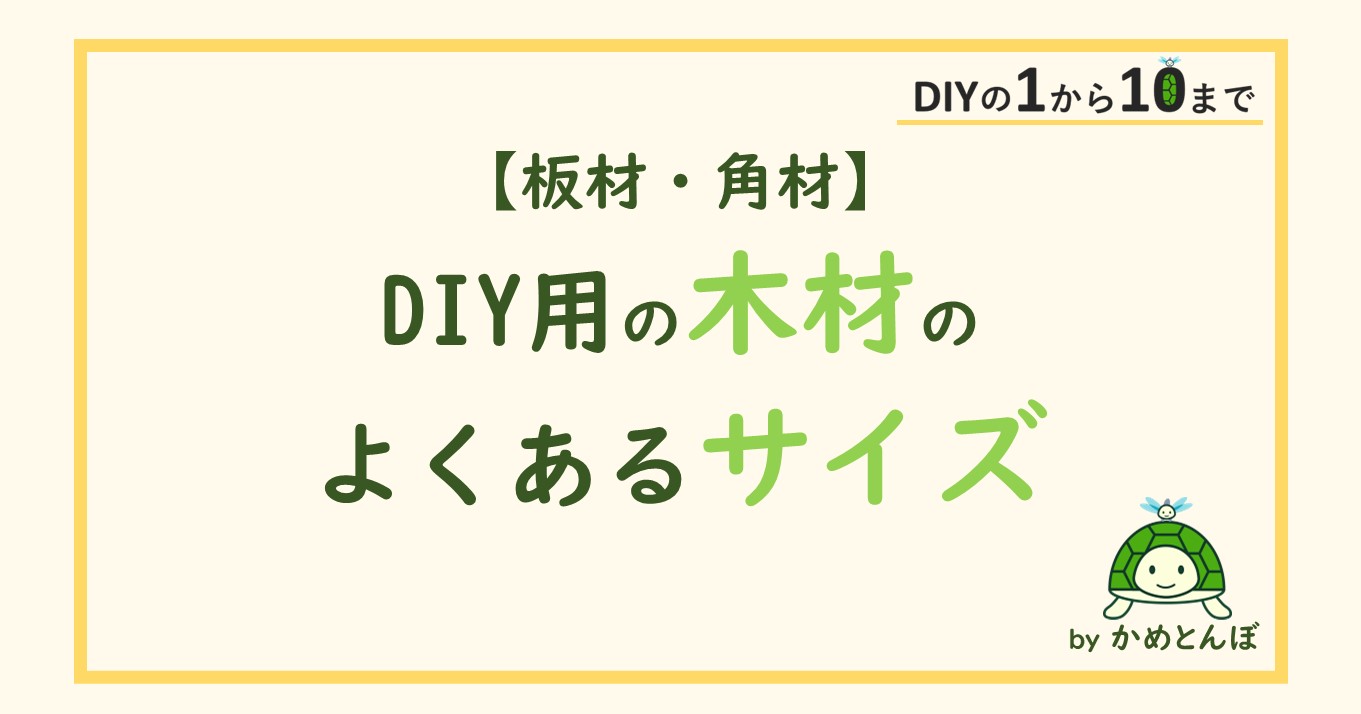
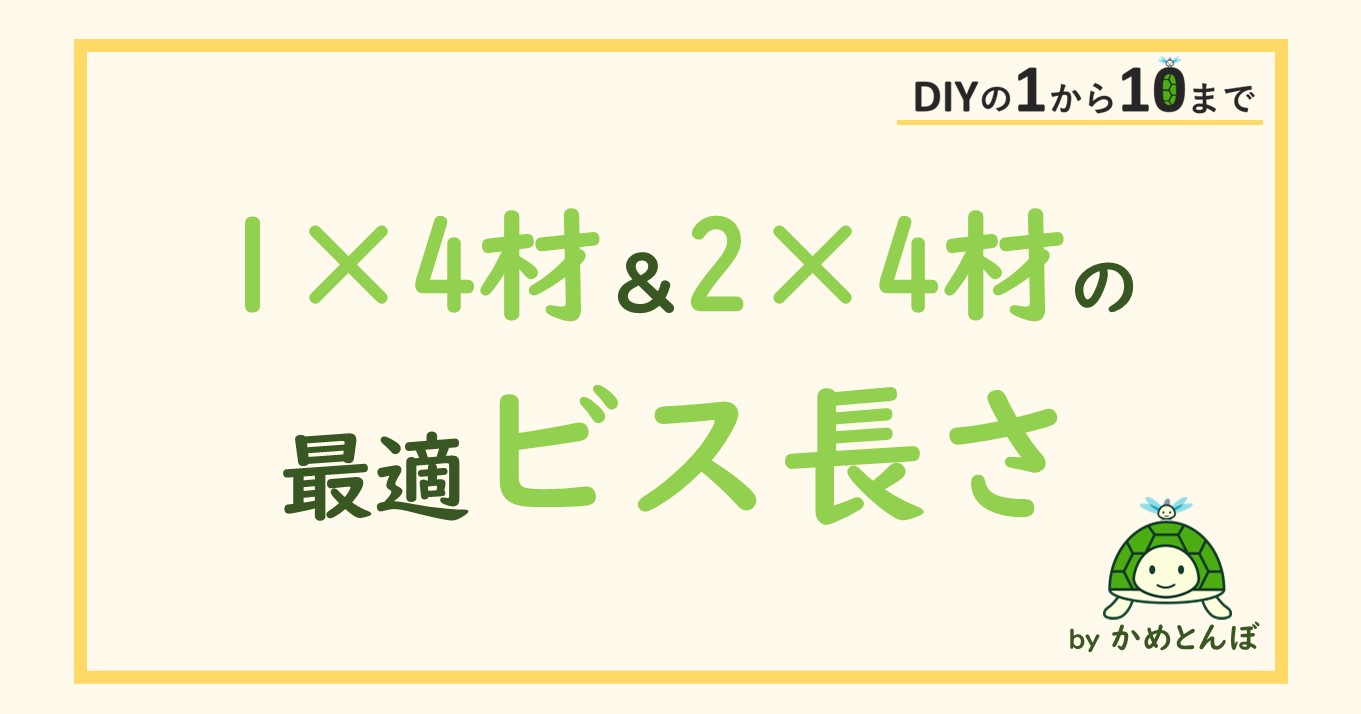
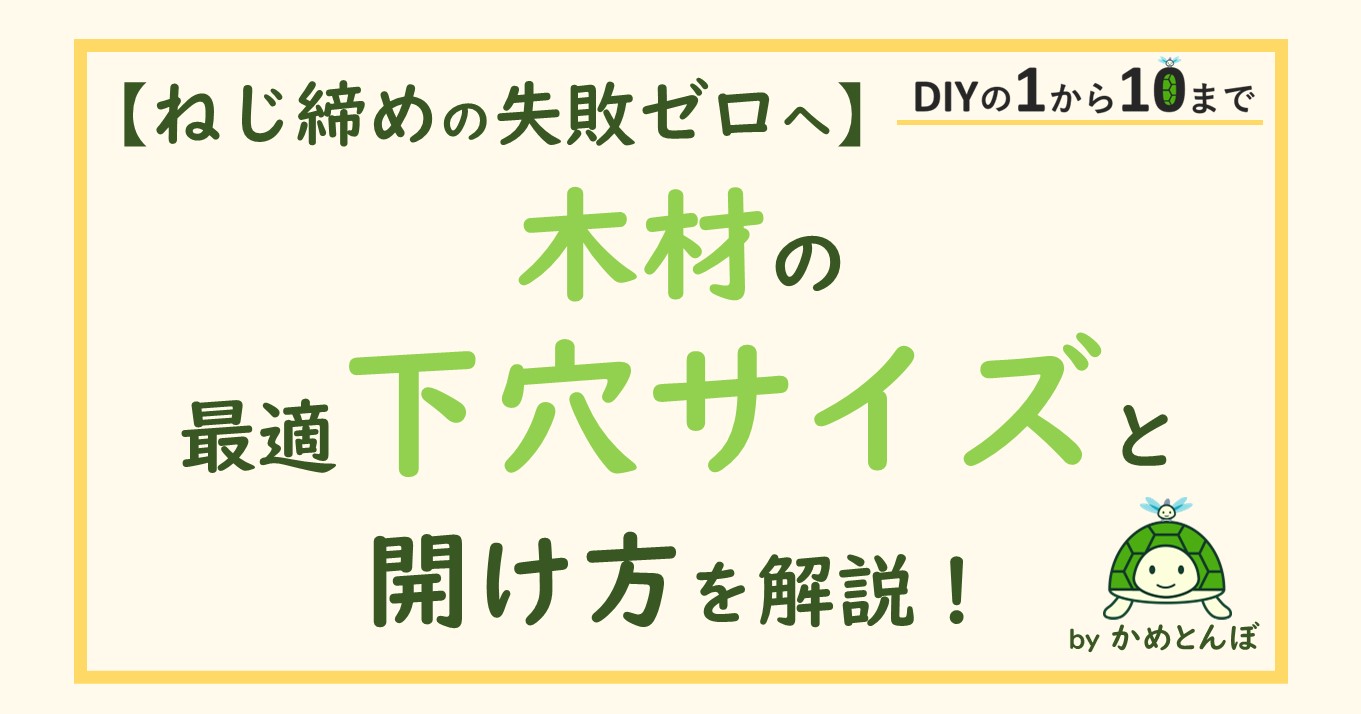
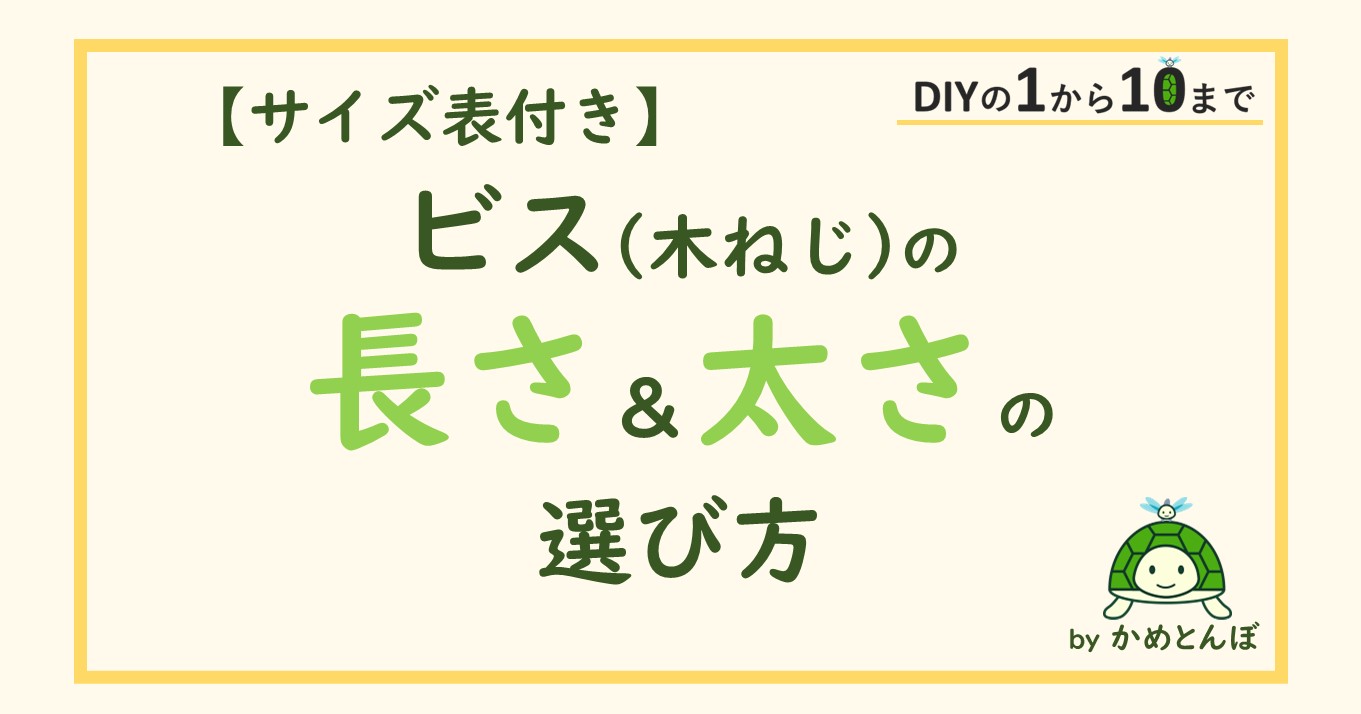


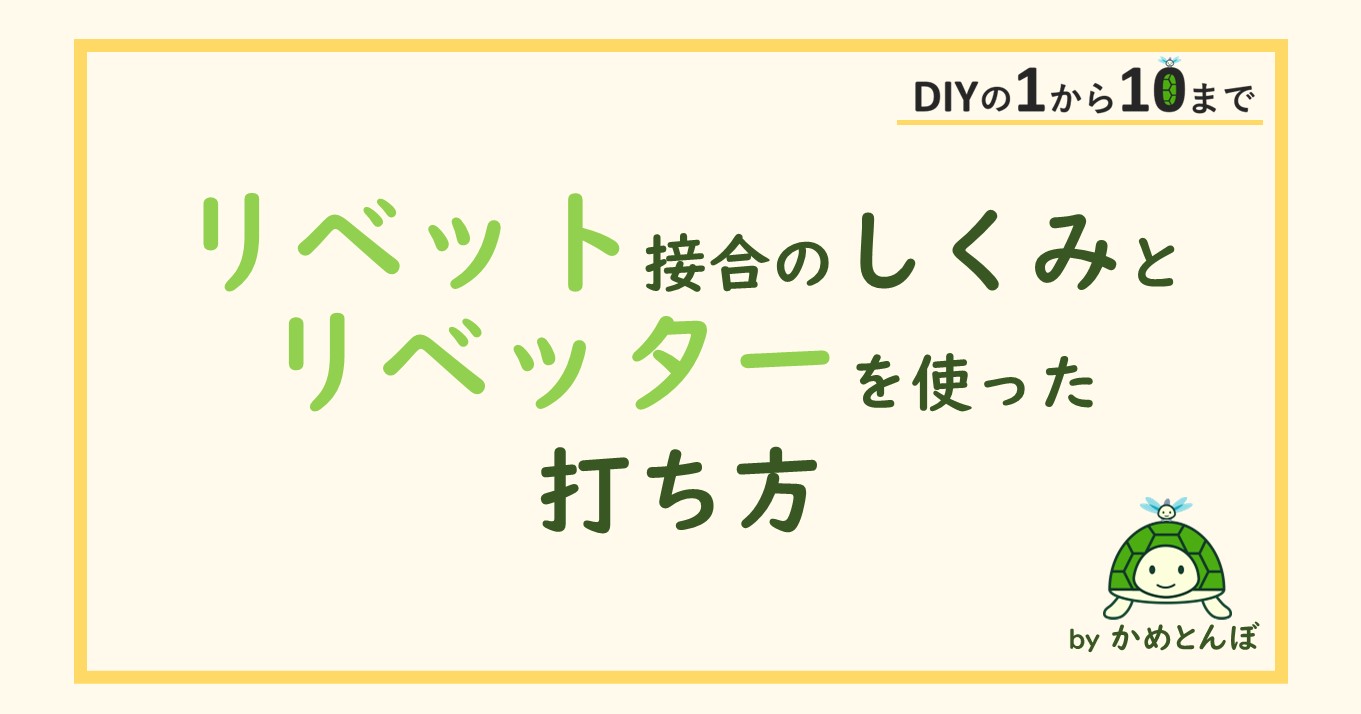
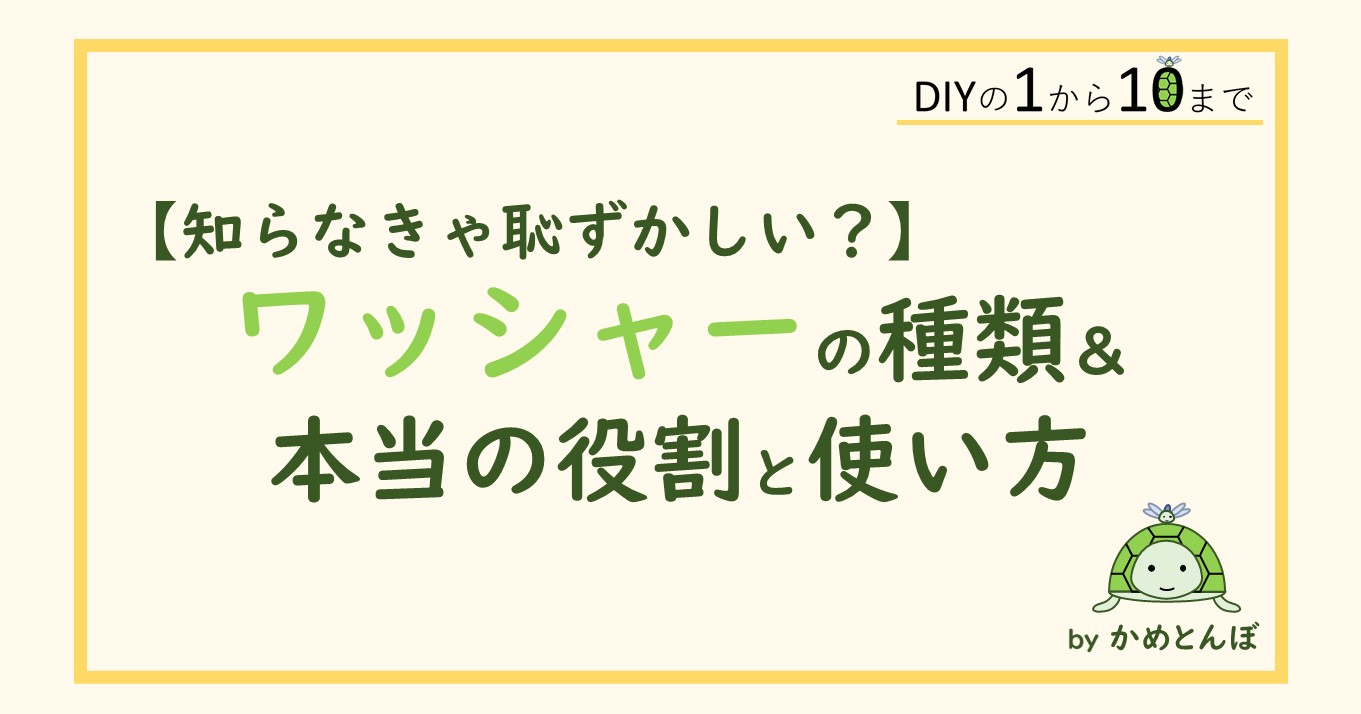



コメント