こんにちは!
かめとんぼです。
今回は、ドリルガイドを使って思い通りに穴あけをするためのポイントと注意点について解説します。
木材に垂直に穴あけをする方法
板材の厚みの部分に穴あけをする方法
丸棒に穴あけをする方法
ドリルガイドを使う時の注意点
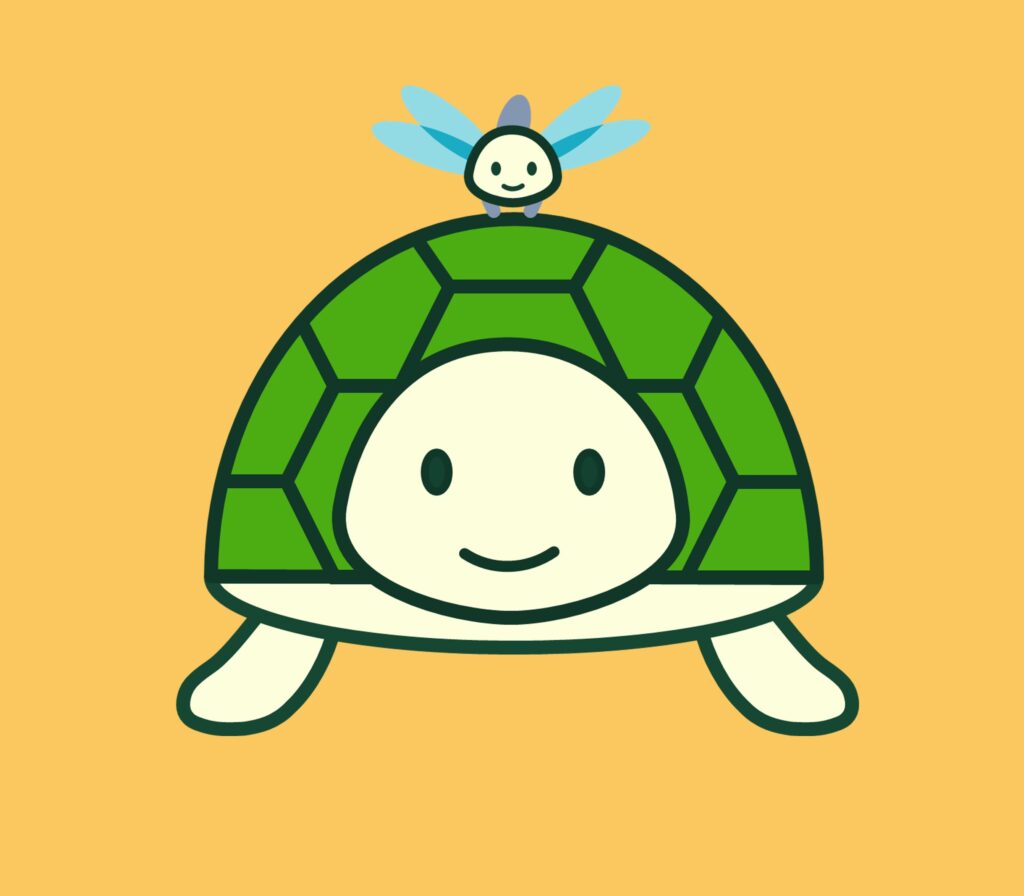
DIYについての知識やポイント、知って得する情報などを紹介します。
現在は賃貸マンションに住んでいて、9割以上の家具を自作しながら理想の部屋づくりを楽しんでいます。
本業は機械設計の仕事をしています。
はじめに
DIYでは、電動ドリルを使って木材や金属に穴あけをすることがよくあります。
ビスを打つための下穴開けや、ダボ継ぎをするための下穴開けなど、特に下穴開けとして穴あけをすることが多いです。
下穴開けは慣れてしまえばそこまで難しい作業ではありませんが、慣れないうちは深すぎる穴を開けてしまったり、斜めに穴を開けてしまったり、また狙ったところに穴を開けることができないなど、意外な落とし穴が多い作業です。
そこでこのブログでは、狙った深さで穴あけをする方法や、初心者におすすめの下穴開けの方法など、初心者でも失敗せずに下穴開けをする方法について解説してきました。

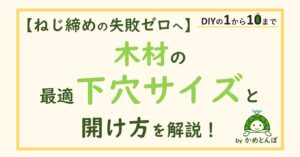
その中でも今回は、木材に垂直に穴を開けたり、丸棒に穴を開けるなど、電動ドリルで「思い通りの穴を開けるための方法」について解説します。
具体的には、思い通りの穴を開けるための便利道具「ドリルガイド」について、使い方や注意点について解説します。
ドリルガイドとは?
ドリルガイドとは、その名の通り電動ドリルを使う時のガイドの事です。
このドリルガイドを使うことで、面に垂直な穴あけや、丸棒などのガイドなしでは難しい場所への穴あけも簡単にすることができます。
面に垂直に穴を開けることができれば、ビスを打った時に見た目の揃った美しい仕上がりにすることができ、初心者でも1ランクレベルの高い見た目の作品を作ることができます。
このドリルガイドには大きく分けて2つのタイプがあり、電動ドリル本体を固定するタイプと、ドリルの先につけるビットをガイドするタイプがあります。
前者のタイプは3000〜8000円程度、後者のタイプは1000〜2000円程度で購入できるので、穴あけが難しいと感じている人や、DIYでの失敗をなるべく少なくしたいと悩んでいる人へはおすすめできる道具です。
ドリルガイドで出来ること
ドリルガイドを使うと、次のような作業を簡単に行うことができます。
垂直に穴あけ
薄い部分への穴あけ(厚み方向など)
丸棒や角部への穴あけ
垂直に穴あけ
ドリルガイドを使うことで、面に垂直に穴あけをすることが可能です。
この、「垂直に穴あけをする」というのはDIYをする上で大切なポイントで、下穴開けで垂直に穴が開いていないと、ビスが曲がって入って不格好になってしまったり、ダボ継ぎでうまく穴同士に入らないといった心配があります。
こういった悩みに対しては、ドリルガイドを使うことで解決が可能です。
ドリルガイドを使えば、その構造から面に垂直に穴を開けることができるため、下穴開けで垂直に穴が開けられない心配点もなくなります。
そのため、下穴が垂直に開けられずにビスを打つと頭が斜めになってしまうことに悩んでいる人や、ダボ継ぎで上手くダボ同士が下穴に入らずに悩んでいる人は、このドリルガイドを使うことで解決が可能です。
薄い場所への穴あけ(厚さ方向など)
ドリルガイドを使えば、板材の厚さ方向への穴あけなど、薄い部分への穴あけも可能です。
薄い場所に穴あけをする場合には、
・垂直に穴を開けること
・厚みの真ん中など、狙った場所に穴を開けること
この2つのポイントが大切です。
薄い場所は、狙ったところに穴を開けることができないと即座に失敗に繋がってしまい、失敗すると木材が割れてしまったりビスの先端が飛び出してしまうことがあります。
この薄い場所への穴あけに対しても、ドリルガイドを使って穴あけを行えば、上で紹介したように垂直に穴を開けることはもちろん、板の厚みのど真ん中などの狙った場所に穴を開けることができるため、失敗の可能性を減らすことが可能です。
このドリルガイドを使って薄い場所への穴あけをマスターできれば、木材の割れ、ビスの飛び出しの無い、見た目のきれいな仕上がりのDIYをすることができます。
丸棒や角部への穴あけ
3つ目のできることは、丸棒や、角材の角部への穴あけです。
これらの作業はガイドなしではとても難しく、慣れている人でも失敗してしまうことが多い作業です。
そのため、通常は丸棒や角部への穴あけは大型の機械で行うことが多いですが、DIYでは大がかりな機械を使ってDIYをするのは現実的ではありません。
そこで、ドリルガイドを使って作業をすれば、機械を使った場合に比べて時間はかかりますが、十分きれいな穴あけをすることが可能です。
丸棒や、角材の角の部分に穴を開けるテクニックを身に付けたら、丸棒同士を組み合わせて枠組みを作ったり、角材同士を90度以外の角度で繋ぐことができるなど、既製品にはない、自分だけのオリジナルの作品を作ることができるようになります。
ドリルガイドのタイプ
ここまで、ドリルガイドの特徴や、ドリルガイドでできることについて見てきましたが、ここからはより具体的にドリルガイドの2つのタイプについて見ていきます。
ドリルガイドには大きく次の2つのタイプがあり、自分の使いたい目的、頻度によって上手く使い分けることが大切です。
本体を固定するタイプ
ビットをガイドするタイプ
それぞれのタイプの特徴について見ていきます。
本体を固定するタイプ
1つ目は、穴あけをする時に使う「電動ドリル」自体を固定するタイプのドリルガイドです。
代表的な物としては、神沢のドリルガイド「K-802」があります。
このタイプの特徴は、大型の機械で穴を開けるように、正確に&垂直に穴あけができることです。
本体の構造はチャックと呼ばれる電動ドリルとビットを取り付ける部分があり、このチャックがガイドに沿って上下に動く構造をしています。
このチャックは両側に立っているガイドに沿って動くため、あらかじめセットした通りの場所に穴あけができ、狙った場所に、垂直な穴あけが可能です。
また、付属のアダプターを使えば丸棒への穴あけもできるため、フリーハンドでは難しい場所にも狙った通りの穴あけをすることができます。
このガイドの使い方は、チャックにドリルビットを取り付け、反対側に電動ドリルを固定します。
そしてこのガイドを穴あけをしたいところにセットして、クランプなどを使ってしっかりと固定します。
ここまでの準備ができたら、ドリルをゆっくりと下げ、ビットが木材についたらドリルの回転を始めます。
注意点としては、ドリルがまだ木材に接していないときに回転を始めると振動でブレて狙ったところに穴あけができない可能性もあるため、必ずビットが木材などに接してから回転を始めるようにしましょう。
しっかりクランプで固定することと、木材に接してから回転を始めることを意識すれば、初めて使う人でも難しい作業はなく、誰でも簡単に狙ったところに穴あけをすることができます。
ビットをガイドするタイプ
2つ目のタイプは、ビットをガイドして穴あけをするタイプです。
中でも人気なのは、SK11のドリルガイドキット「SGK-6」です。
このタイプは、値段が1000〜3000円と安いこと、また本体がコンパクトで気軽に使えることがポイントです。
本体は、木材などに乗せる真ん中に円筒形の穴の空いたベースの樹脂部品と、その円筒形の中に入れる金属のガイド部分でできています。
ビットのガイドとなる金属の部品はスチールで出来ており、慣れない時にビットが当たってしまっても削れにくくなっています。
そのため、使う時に慎重になりすぎる必要が無く、初心者でも安心して使うことができます。
このSK11のドリルガイドは、ベースとなる樹脂部品に特徴があります。
平らな底面を木材などにぴったりと押さえつけることで面に垂直に穴が開けられるほか、ベースの裏面には溝がついており、その溝に丸棒などをはめることで丸棒や角部への穴あけも可能です。
また、ベースに開いている穴に釘などを差し込み、板を挟むようにすれば簡単に幅のセンター出しもできます。
このように、このドリルガイドを使えば垂直な穴あけや丸棒への穴あけなど、狙った通りに穴あけができるため、棚づくりや収納作りなどのDIYで行う一通りの穴あけ作業をより簡単に、正確にすることが可能になります。
このタイプのドリルガイドを使う時に注意しておきたいポイントは、ベースの樹脂部品と金属のガイドのすき間が無いように準備することが大切です。
樹脂は、少し専門的な話しになりますが、成形して作るときの寸法が大きくばらつくため物によって出来栄えが異なってしまいます。
そのため、樹脂のガイドと金属のガイドが隙間ができてしまい、この隙間によって開けた穴の位置がずれてしまう場合があります。
このすき間を埋めるために、このタイプのガイドを使う前には金属の部品の外側にマスキングテープなどを巻き、がたつきがないようにしてから使用するとより正確に狙った通りに穴あけをすることができます。
また、このタイプのドリルガイドを使う時にも、クランプを使ってガイドを木材などにしっかりと固定して使うことで、より正確に、ミスすることなく作業をすることができます。
ドリルガイドを使うときの注意点
最後に、これらのドリルガイドを使う時の注意点についてまとめます。
一部、上に書いた内容と重なることもありますが、これらのポイントに注意すればより確実にドリルガイドを使いこなすことができます。
クランプでしっかりと固定する
ビットが木材に当たってから回転を始める
インパクトドライバーは使わない
ゆっくり穴あけをする
クランプでしっかりと固定する
まず1つ目の注意点は、クランプを使ってドリルガイドをしっかりと固定することが大切です。
クランプを使うと、しっかりとガイドを固定できて狙った通りに穴があけられるだけではなく、ガイドを手で固定する必要が無くなります。
そのため、電動ドリルを両手でしっかりと持って動かすことができ、特にDIY初心者のうちなど、作業に慣れていない時にも安心して電動ドリルを使うことができます。
クランプについてはこちら

ビットが木材に当たってから回転を始める
この注意点も大切なポイントで、電動ドリルを下げていき、木材などに当たってからドリルの回転を始めるように注意しましょう。
本体を固定するタイプのガイドでは、ビットがまだ空中にあるときに回転を始めるとビットがぶれて狙った通りの所に穴あけが出来ない心配があります。
また、ビットをガイドするタイプでは、木材に当たる前に回転を始めるとこちらもビットがぶれて金属のガイドに当たり、ガイドが削れてしまう心配があります。
そのため、どちらのタイプのガイドを使う場合にもしっかりと木材などにビットが当たってから回転を始めるように注意しましょう。
インパクトドライバーは使わない
穴あけをするときにインパクトドライバーを使う人もいるかと思いますが、ドリルガイドを使う時にはインパクトドライバーは使わないように注意しましょう。
インパクトドライバーは、負荷がかかるとインパクトの動きでビットが上下するため、そもそも正確な穴あけに向きません。
加えて、ビットが上下するのに従ってガイドが動いて狙ったところから外れてしまうため、ガイドの良さが無くなってしまいます。
そのため、ドリルガイドを使うような正確な穴あけをしたい場合には、インパクトドライバーではなく電動ドリルドライバーを使うようにしましょう。
ゆっくり穴あけをする
ドリルガイドを使う場合には、いつもより少しゆっくり目に穴あけをしましょう。
ゆっくりというのも、ビットの回転のスピードではなく、電動ドリルを下げていくスピードをいつもよりゆっくりにしていきます。
これにもしっかりとした理由があって、ドリルガイドを使う場合にはビットの先の穴を開けている部分が見えにくくなります。
そのため、どのくらいのスピードで穴が開いているかが見えないのはもちろん、ビットが何かに引っかかっていたり、狙ったところからずれている場合にも気づきにくいです。
こういったトラブルに早めに気づくためにも、いつもより少しゆっくり目にドリルを動かして注意しながら穴あけをすることで、よりきれいな仕上がりになります。
まとめ
今回は、ドリルガイドを使って思い通りに穴あけをするためのポイントと注意点について解説しました。
このブログでは、電動ドリルやインパクトドライバーについて、DIY初心者にも分かるように徹底的に解説しています。
特に電動ドリル/ドライバーの特徴、使い方のポイントや、様々な悩みの解消法に関しては、一番わかりやすいサイトを目指して日々改良をしています。
その他にも、DIYについての知識やポイント、知って得する情報について紹介していきます。
一緒に学んで、楽しいDIYにしましょう。
かめとんぼ
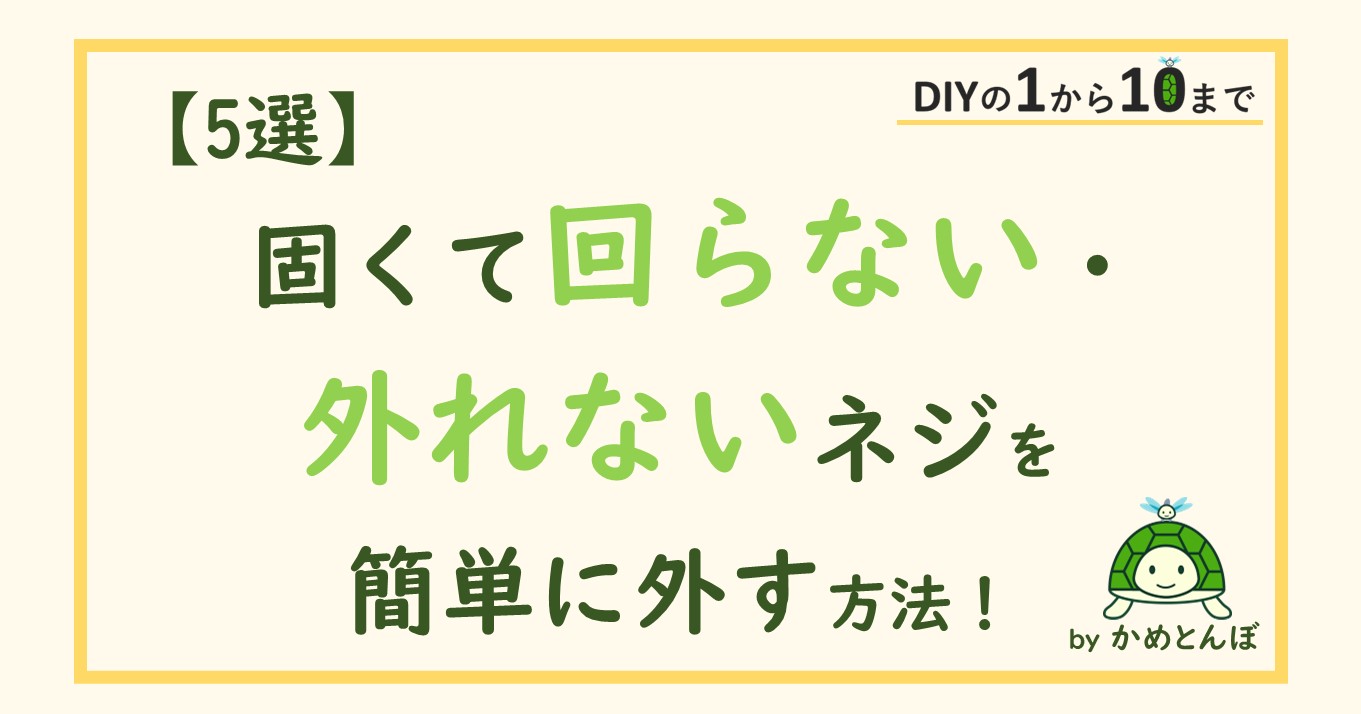
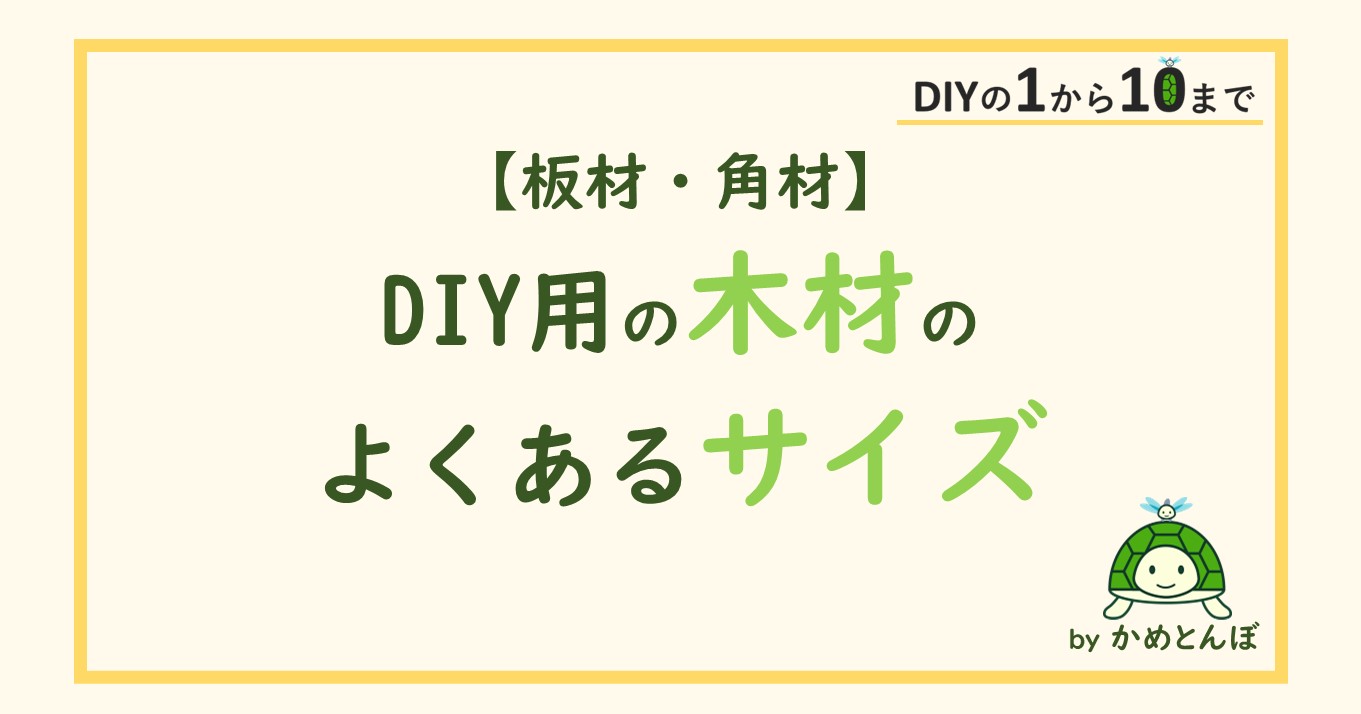
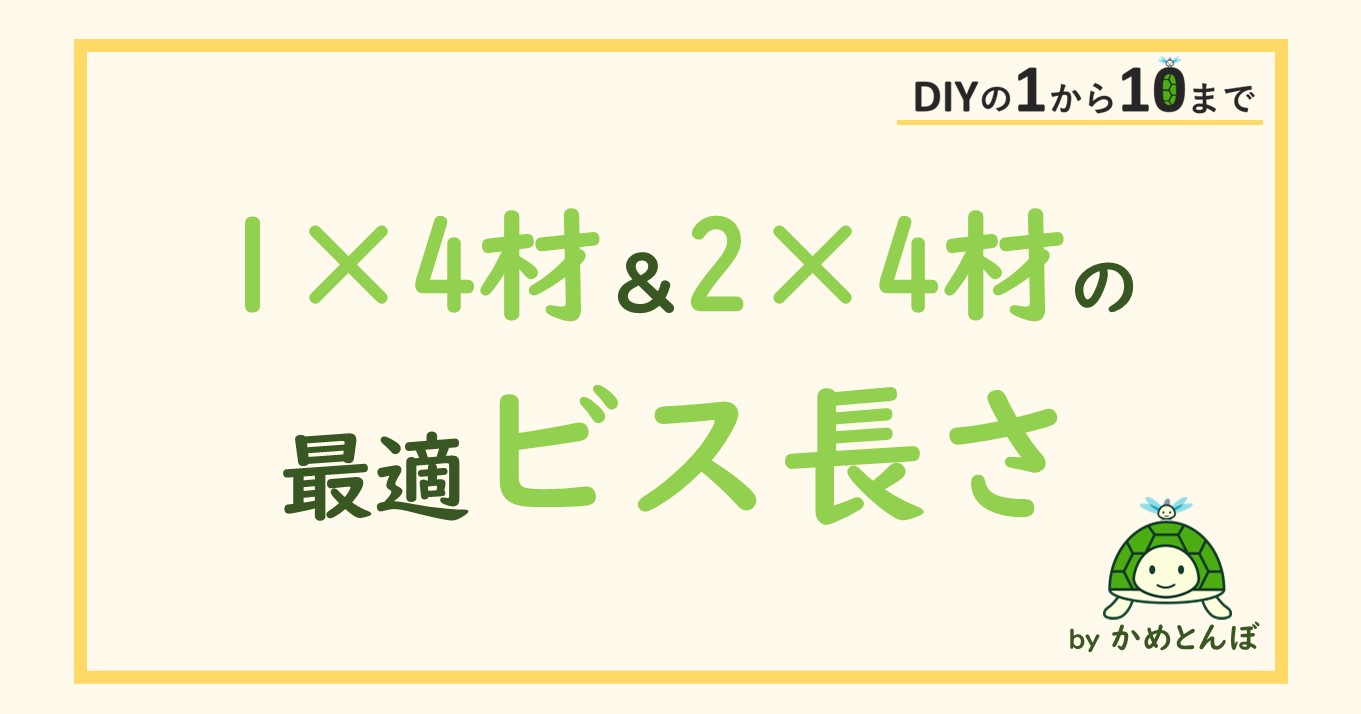
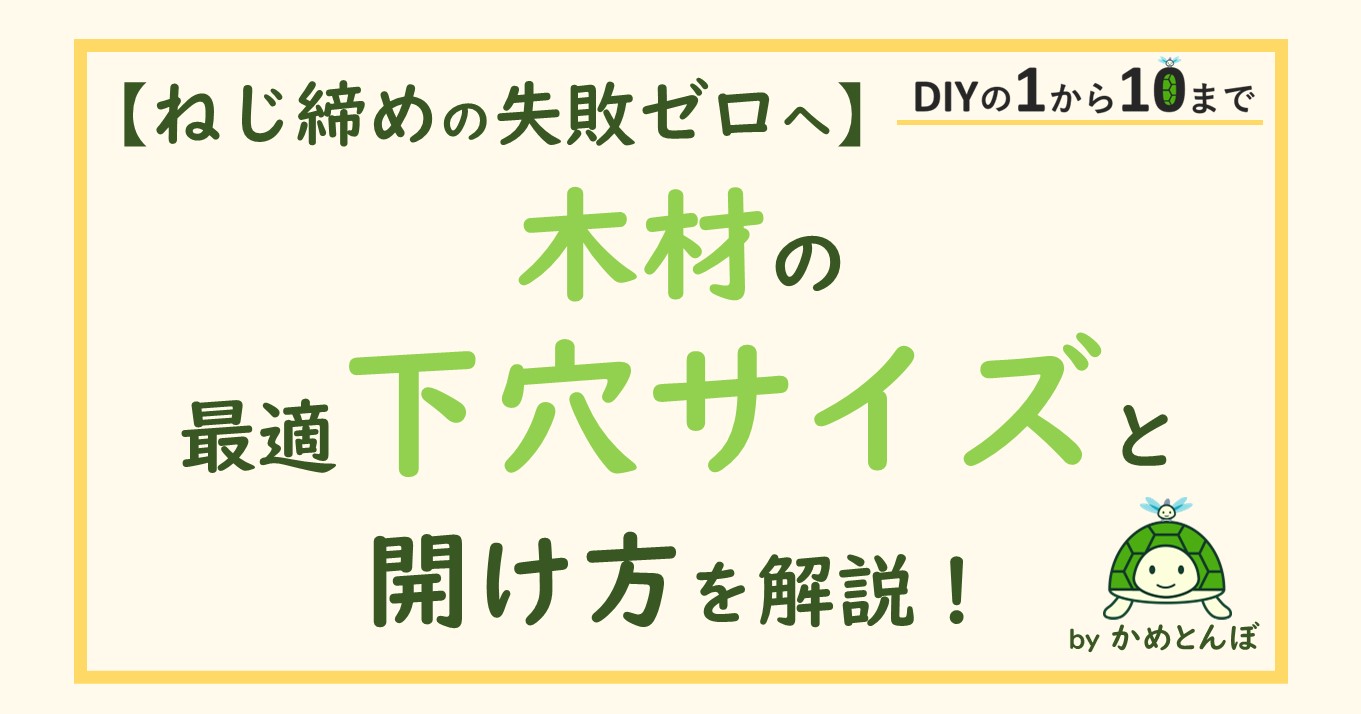
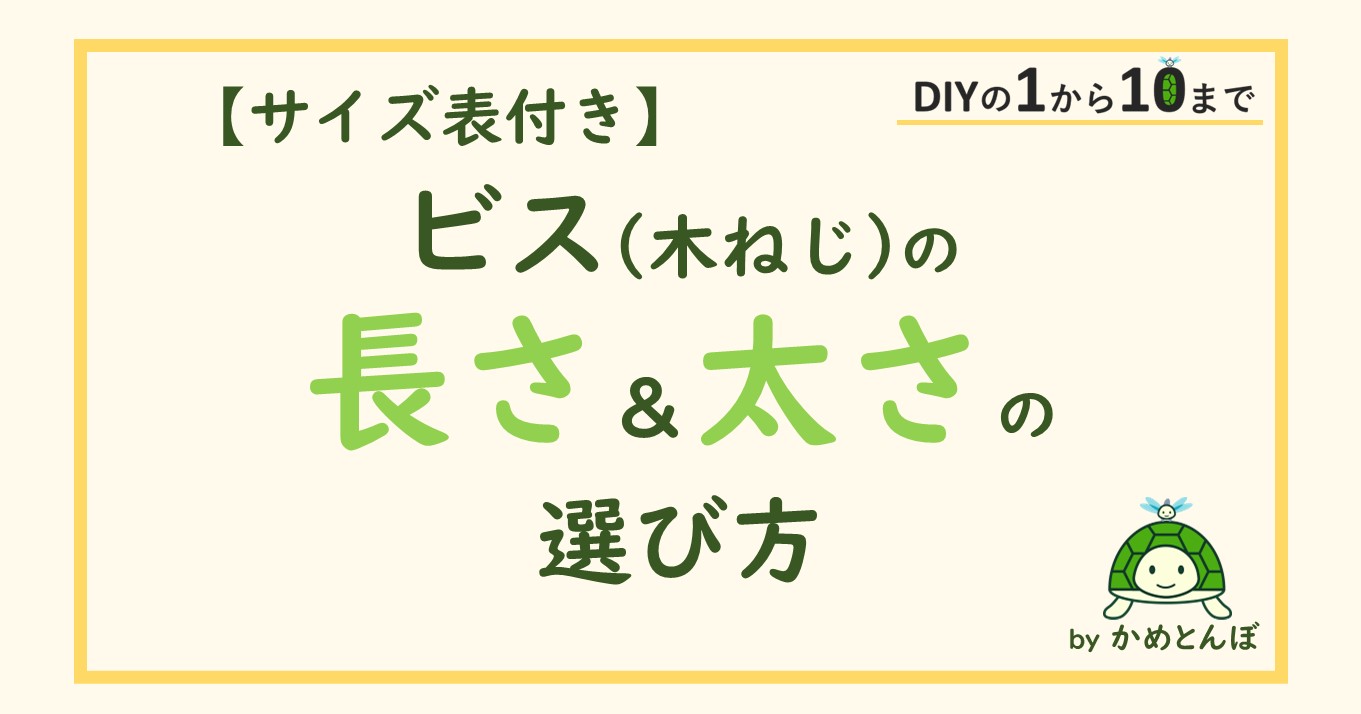


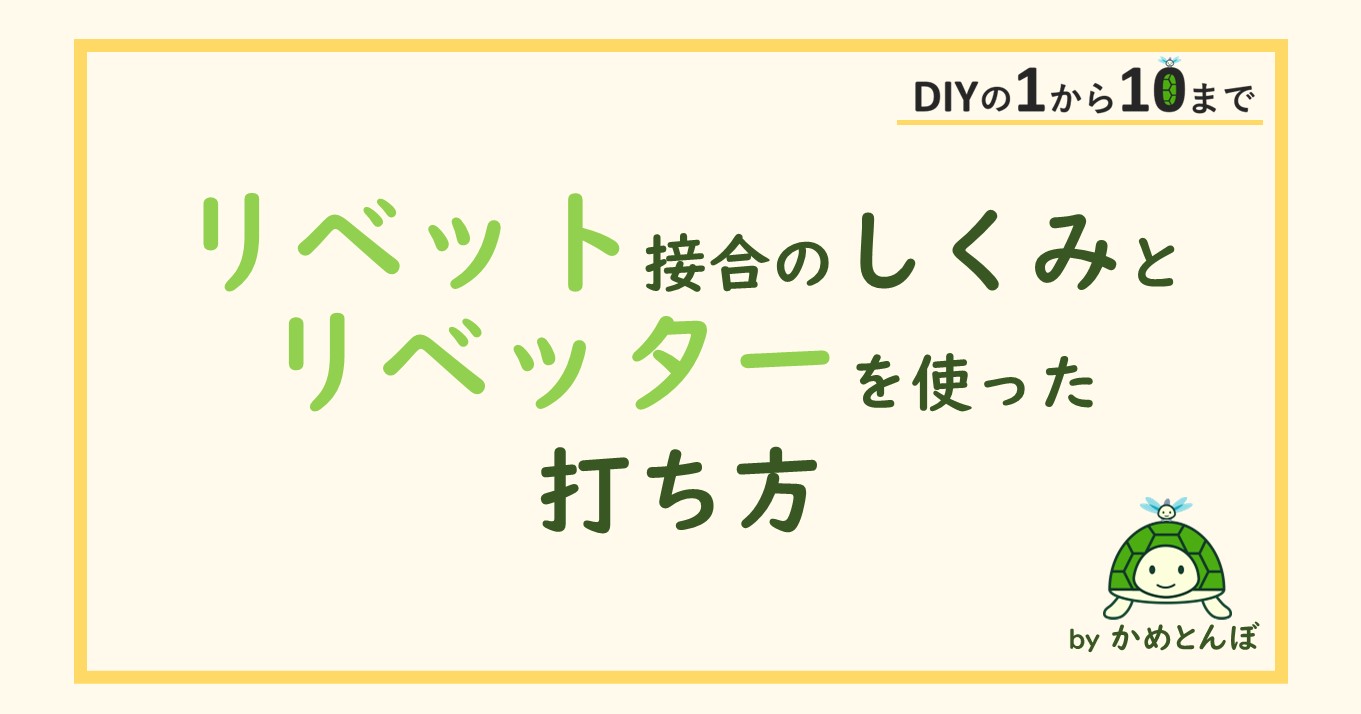
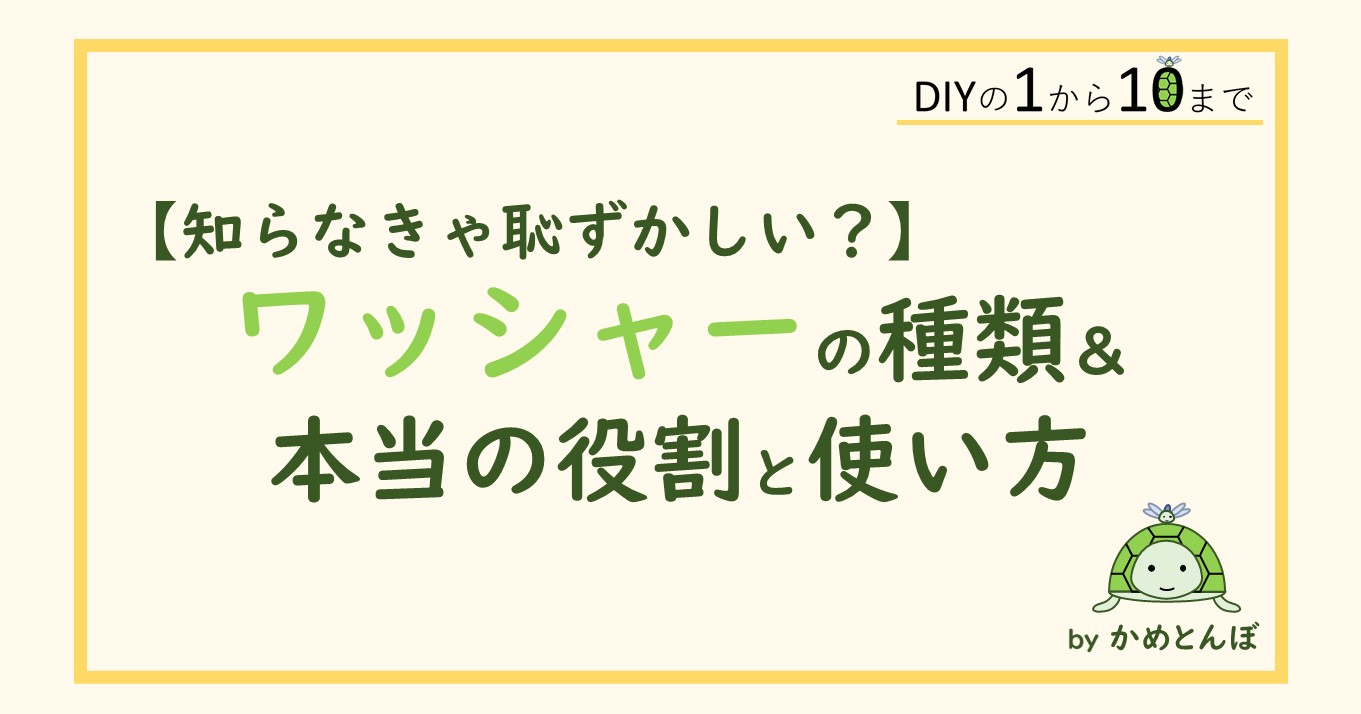



コメント